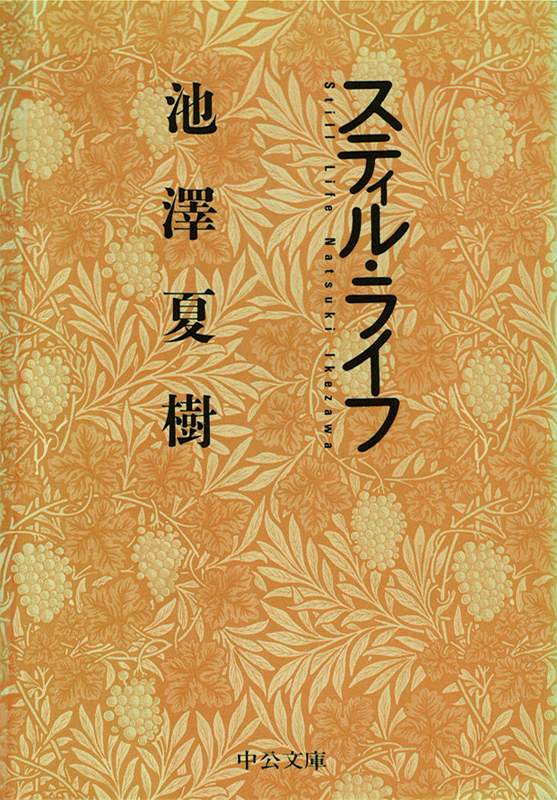スティル・ライフ
遠いところへ、遠いところへ心を澄まして耳を澄まして、静かに、叙情をたたえてしなやかに—。
清新な文体で、時空間を漂うように語りかける不思議な味。ニュー・ノヴェルの誕生。中央公論新人賞・芥川賞受賞作『スティル・ライフ』、受賞第一作『ヤー・チャイカ』を収録。
作品情報
< 目次 >
スティル・ライフ
ヤー・チャイカ
出版社:中央公論社、後に中央公論新社
出版年月:1991/12
あとがき などコンテンツの違いのある部分:
解説(須賀敦子)
この作品のレビューを投稿しませんか?
cafe impala では、読者のみなさんのレビューを募集しています!
» レビューについて
レビュー投稿ガイドライン
- 投稿は400字以上を目指してください。
- 投稿いただいたレビューは、cafe impala 編集部の承認後、サイトに表示されます(投稿後、すぐに表示はされません)。
- サイトに表示されたレビューは、impala.jp 内の複数媒体 [単行本版/文庫本版/impala e-books (電子書籍)版] に共通して掲載される場合があります。
- 投稿レビューの著作権は、投稿された方にあります。ご自身のレビューは、後日他のサイト等でも利用することができます。
- 投稿に際して入力していただく個人情報は、cafe impala の制作運営に関連するcafe impala編集部、impala e-books編集部からの連絡に限り利用させていただきます。
この作品のレビュー
-
『 スティル・ライフ 』
宇宙から飛来する微粒子の放つ光を、グラスの水の中に待ち受けるような奇妙な男、佐々井。染色工場でアルバイトをしながら無為に近い日々を過ごす「ぼく」は、大きな重力をもつ天体に、小さな星が知らず知らずのうちに引き寄せられるように、佐々井の世界へと捕らわれてゆく。静かに、少しずつ、ぼくの軌道は楕円に伸びてゆく。
「雪が降るのではない。雪片に満たされた宇宙を、ぼくを乗せたこの世界の方が上へ上へと昇っているのだ」
「ハトの灰色の輪郭はそのまま透明なタイム・マシンの窓となる。長い長い時の回廊のずっと奥にジュラ紀の青い空がキラキラと輝いて見えた」
宮沢賢治が空のたかみから素敵な化石を発掘してみせたように、池澤夏樹は現実世界から、硬質な抒情とよぶべき星のかけらのような言葉の連なりを取り出してみせる。その手管があまりにも巧みなので、この作品が実は犯罪小説であることを我々は忘れてしまう。
そう、この作品は決して童話などではない。バブル景気という沸騰した偽の現実に、日本人がボイルされているまさにその最中に、詩人の深く暗い懐から差しだされた、刃渡りが短いが恐ろしいほどによく切れる、ナイフのようなノワールなのだ。
発表から30年以上を経ても、我々の頭上で怜悧に瞬き続ける、現代日本文学の北極星。
高橋 園 -
『 スティル・ライフ 』
スティル・ライフは、読むたびに感想が変わる気がします。
初めて読んだときは、いまよりもっと人生が辛かったときで、とにかく救われるために、救われたくて、読み始めたことを覚えています。それは、冒頭の
「この世界がきみのために存在すると思ってはいけない。世界はきみを入れる容器ではない。」
という一節に、ああ、だれかにこういう様なことを言ってほしかったんだと感じたからです。
暖かいのか冷たいのか嬉しいのか悲しいのか、正体の分からないような気持ちだったけれど、はじめて誰かの言葉が納得できたような、そんな出会いが冒頭にありました。池澤さんのことが大好きなので、こんなことを言うのはいけないのかもしれないし、間違っていたら叱ってほしいくらいですが、この作品が芥川賞を取ったということに悲しくなるときがあります。
いまを生きるということは、透明人間にもなれないし、心が星に直結しないし、ニュートリノの飛来は感知できないし、山や高原や惑星や星雲と同じディメンションの希薄な存在にもなれない
やっぱりそういうことなんだと、突き付けられたような気がするからです。社会生活や言語表現は、いろんなことを試みるが(いまはSNSとかもあって大変)、それでもわたしたちが行きたい場所はひとつだよね、と思います。
それに近い場所を、わたしはスティル・ライフから感じてしまいます。どんなに悲しいことが起きても、この小説があれば、わたしはこれからも生きていけるだろうと思いました。
遠い地での戦いの恐怖や血の匂いや容赦ない死は、想像したって分かることはない。その事実がどんなに最悪でも、ちゃんと生きていこうと思います。わたしが生まれたのは、この作品が発表されたよりも遅いので、まるで池澤さんの足跡をずっとあとになってから辿っているような感じなのかもしれませんが……わたしにとっては、あまりにも友達のような作品です。
さいごの佐々井と「ぼく」の会話が大好きで、読むと泣きそうになります。どうせ生きているなら、わたしもあんなふうについ喋りすぎちゃって、存在がまっぷたつに(あるいはもっとたくさん)散っていくような感覚を何度でも味わいたい。
書いてくださり、ありがとうございます。真子